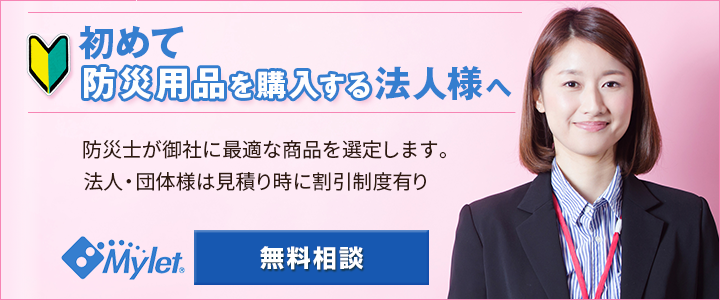地震発生時や、過去の震災を振り返る時良く目にする単位が「マグニチュード」です。マグニチュードと同じく頻繁に登場する単位に「震度」があり「マグニチュードは何を表す単位?」「震度とマグニチュードは違うの?」といった疑問を持つ方もいるかもしれません。本記事では、マグニチュードの概要や由来、震度との違い、地震の規模によりどの程度の被害が想定されるかの目安について解説します。
Contents
マグニチュードの基本知識
マグニチュードの概要や由来などの基本情報を紹介します。
マグニチュードとは
マグニチュードとは、地震の規模・エネルギーを表した単位で「M」と表記されます。Mが1増えると地震のエネルギーは約32倍、2増えれば、32×32=約1000倍になるのが特徴です。
つまり、M8の巨大地震(1923年の関東大震災を引き起こした関東地震はM7.9)のエネルギーは、M6の中規模地震の約1000回分に相当することになります。
マグニチュードの由来
マグニチュードは、1935年にアメリカの地震学者チャールズ・リヒターによって定義されました。マグニチュードは、大きさを表すラテン語「magunis」に、性質や状態の抽象名詞を作る「tude」を付けた英語「magnitude」です。なお、定義したチャールズ・リヒターにちなみ、マグニチュードは「リヒター・スケール」とも呼ばれています。
日本で使用されているマグニチュードの種類
地震の規模・エネルギーを示すマグニチュードは、重さ・長さのように直接測ることができません。そのため、マグニチュードには観測する地震計の種類、計算方法によってさまざまな種類があります。世界的な統一規格はなく、日本では「気象庁マグニチュード(Mj)」と「モーメントマグニチュード(Mw)」の2種類のマグニチュードが採用されています。
発生した地震に対して、基本的には気象庁マグニチュードが代表値として使われています。気象庁マグニチュードは、約100年間一貫して使用されてきたマグニチュードのため過去の地震の規模との比較がしやすいこと、地震発生からマグニチュードをすぐに求められることが理由です。
モーメントマグニチュードは巨大地震の規模を求められる、物理的な数値を算出できるのが特徴です。そのため、気象庁マグニチュードではマグニチュードの数値を適切に求められない場合には、モーメントマグニチュードが代表値として使われることもあります。
マグニチュードの目安や正しい見方
マグニチュードの数値ごとの目安と、正しい見方について解説します。
マグニチュードの目安
マグニチュードは、数値によって以下の地震の規模で呼ばれています。
| マグニチュードの数値 | 地震の規模の呼び方 |
|---|---|
| 8以上 | (巨大地震) |
| 7〜 | 大地震 |
| 5〜7 | 中地震 |
| 3〜5 | 小地震 |
| 1〜3 | 微小地震 |
| 1未満 | 極微小地震 |
マグニチュードの正しい見方
 マグニチュードは、最初発表された数値から順次更新されます。地震で発生する地震は時間の経過ごとに震源に近い観測点へ順次到達するため、マグニチュードの算出に活用できる観測点数やデータの種類が増えていくためです。地震発生を覚知してから順次解析を実施し、マグニチュードはより適切なものに更新されていきます。地震発生後は、最新の地震情報や津波警報などを随時確認し、記載しているマグニチュードが更新されていないかもチェックすることをおすすめします。
マグニチュードは、最初発表された数値から順次更新されます。地震で発生する地震は時間の経過ごとに震源に近い観測点へ順次到達するため、マグニチュードの算出に活用できる観測点数やデータの種類が増えていくためです。地震発生を覚知してから順次解析を実施し、マグニチュードはより適切なものに更新されていきます。地震発生後は、最新の地震情報や津波警報などを随時確認し、記載しているマグニチュードが更新されていないかもチェックすることをおすすめします。
震度とマグニチュードの違いと震度の目安
マグニチュードと同じく、地震の規模を示す数値に震度があります。震度とマグニチュードの違いと、震度の数値ごとの目安について解説します。
震度とは
震度とは、特定の場所での地震の揺れを表した数値です。地震が発生すると、震度は全国に4000ヶ所以上ある計測震度計で、自動的に観測されます。なお、地震の揺れは地中の柔らかさ・硬さや地形によっても変化するため、同じ町内でも場所によっては震度が1ほど異なることもあります。 以前は震度は8階級まで、さらに体感や建物の倒壊率など、計測者によって誤差が生じやすい方法や指標によって震度が決められていました。1996年に震度の階級数が10階級に改正され、さらに震度計で測った加速度などの客観的な指標や方法から、震度が決められるようになりました。
マグニチュードと震度の関係
マグニチュードは地震そのものの規模やエネルギーの強さを表すのに対して、震度は特定の場所での地震の揺れを表します。マグニチュードが大きければ全体の震度が大きくなるのではなく、震源に近ければ近いほど、一般的に震度は高くなります。つまり、マグニチュードが大きな地震でも、震源から遠ければ震度は小さくなり、逆にマグニチュードが小さな地震でも、震源から近ければ震度は大きくなります。 たとえば2011年3月11日に発生した東日本大震災はマグニチュード9.0、震源は三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近です。そのため震源に近い岩手県や宮城県などでは震度6強や7が観測され、関東では震度4から5強、東海地方や北海道では震度3から4と、震源から遠くなるにつれて震度は小さくなります。
参考:内閣府_東日本大震災
震度の目安
日本の震度は「気象庁震度階級」が採用されており、揺れの度合いが10階級に分かれています。震度別に実際に発生する可能性のあることや、体感について以下にまとめました。
| 震度 | 実際に起きる可能性があること、体感 |
|---|---|
| 0 | ・人は揺れを感じない |
| 1 | ・屋内で静かにしている人は、揺れをかすかに感じることがある |
| 2 | ・屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる ・ぶらさがっている電灯などがわずかに揺れる |
| 3 | ・屋内にいるほとんどの人が揺れを感じる ・棚にある食器類が音を立てることがある |
| 4 | ・歩行中の人も揺れを感じる ・眠っている人のほとんどが目を覚ます ・不安定な置物が倒れることもある ・ぶらさがっているものが大きく揺れる |
| 5弱 | ・多くの人が、周りのものにつかまるなど身の安全を図ろうとする ・一部の人は行動に支障を感じる ・食器や本が落ちたり、家具が移動したりすることがある |
| 5強 | ・多くの人が非常に恐怖を感じる ・多くの人の行動に支障が生じる(ものにつかまらないと歩けないなど) ・食器や本の多くが落ち、タンスなどの重い家具も倒れることがある ・弱いブロック塀が崩れることがある |
| 6弱 | ・立っていることが困難になる ・固定していない重い家具の多くが移動、転倒する ・ドアが開かなくなることが多い ・壁のタイルや窓ガラスが破損し、落下することがある ・揺れに強くない木造建物に、瓦の落下や建物の傾きが生じることがある |
| 6強 | ・はわないと移動できない ・固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する ・戸が外れて飛ぶことがある ・ゆれに強くない木造建物の多くが傾いたり倒れたりする ・大きな地割れや地すべりが起きることがある |
| 7 | ・大きな揺れのため自分自身の意思で動作や移動ができない ・大きな地割れや地滑り、山崩れが発生する ・ゆれに強くない木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる ・ゆれに強い木造建物でも、まれに傾くことがある ・ゆれに強くない鉄筋コンクリートの建物では、倒れるものが多くなる |
災害用トイレセット マイレット mini-10の使い方は以下の動画よりご確認ください。
まとめ
マグニチュードの基本情報とともに、震度との違いや目安について解説しました。マグニチュードと震度は、地震の多い日本では日常的に目にする単位です。地震が発生したらマグニチュードや震度を確認し、適切な行動を取るようにしましょう。
関連記事
南海トラフ地震臨時情報とは?発表時の対応方法を防災士が解説
地震被害後本当に困ったことは「トイレ」!やっておきたい備えとおすすめ商品を解説