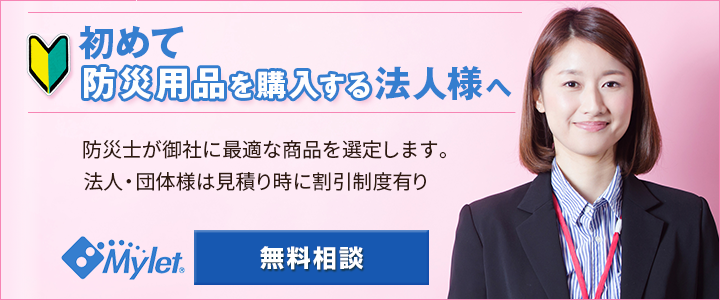万が一の火災から家族や財産を守るために、素早く火災を検知、周知するのが火災報知器です。アパートやマンションなどの集合住宅はもちろん、戸建て住宅にも家庭用火災報知器の設置は義務化されています。今回は、火災報知器の概要や種類とともに、設置基準や適切な設置場所について解説します。
Contents
火災報知器の役割
火災報知器とは、家庭や建物内で発生した火災を即座にキャッチし、音や音声によって火災発生を知らせる機器です。火災は火や煙の目視、焦げ臭い匂いなどでも感じ取れますが、就寝中や今いる部屋から離れた場所で火災が発生した場合、気付きが遅くなり逃げ遅れてしまう可能性があります。そこで火災の煙をすばやく感知し、警報を発することで火災を周知し、迅速な初期消火や避難につなげるのが火災報知器の役割です。
参考:総務省消防庁_住宅用火災警報器Q&A
火災報知器の種類
火災報知器はオフィスや工場といった事業所だけでなく、新築・既存問わず住宅にも設置義務があります。火災報知器の設置場所別の種類を紹介します。
自動火災報知設備
自動火災報知設備とは、火災によって発生する熱や煙、炎を自動的に感知し、火災発生を知らせる設備です。自衛消防組織設置対象物及び防災管理義務対象物法第8条に該当する防火対象物に設置され、受信機の火災信号を発信します。
自動火災報知設備は、消防設備の工事や点検・整備に関する国家資格である消防設備士甲種4類の取得者でなければ、設置工事ができません。
特定小規模施設用
特定小規模施設用の火災報知設備とは、無線式の連動型警報機能付感知器を搭載した報知器です。配線工事不要で設置できるため設置がしやすいことに加えて、感知元から離れた部屋でも、素早く火災発生を把握できる特徴があります。
住宅用
住宅用火災警報器とは、主に一般住宅・家庭に取り付けられる火災報知器です。住宅での火災発生時熱や煙を検知し、音声やブザー音ですばやく知らせることで、就寝中や離れた部屋から迅速に避難できます。
消防法では、住宅用火災報知器の寝室、および寝室が2階以上のフロアの場合火災の煙が集まりやすい階段室(階段のみの空間)への設置を義務付けています。住宅用火災警報器の設置には電気関連の工事は不要で、無資格でも設置可能です。
火災報知器の主な設置基準
消防法によって定められている各火災報知器の設置基準を以下の一覧にまとめました。
| 自動火災報知設備 | 住宅用火災報知器 | |
|---|---|---|
| 消防法の条例 | 消防法第17条 消防法施行令第21条等 |
消防法第9条の2 消防法施行令第5条の6等 |
| 設置義務の対象物 | 一定規模以上の事業所(宿泊施設、飲食店、物販店等) | 住宅(新築、既存問わない) |
| 警報音に関する規定 | ・ 音圧は取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で90(音声により警報を発するものにあっては92)デシベル以上であること ・ 階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に有効に報知できるように設けること ・ 各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けること |
警報音(音声によるものを含む)により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値の電圧において、無響室で警報部の中心から前方1m離れた地点で測定した値が、70デシベル以上かつ、その状態を1分間以上継続できること |
| その他の規定 | 特になし | 警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器については、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること |
火災報知器の設置場所

具体的な火災報知器の設置場所について解説します。
自動火災報知設備の設置場所
自動火災報知設備は受信機・感知器からなり、それぞれに設置場所の要件が定められています。それぞれを解説します。
受信機設置場所の要件
- 常時誰かがいる場所(防災センター、守衛室など)
- 共同住宅の管理人室など(ただし、無人となる場合は非常時に入室できる構造とする)
上記以外の場所で管理上やむを得ない場合は、玄関ホール、廊下等の共用部で、避難上支障とならない位置
- 開放廊下等の共用部の場合は、防湿、防塵、防眩及び悪戯防止のための収納箱等内に設置する
- 温度または湿度が高く、衝撃、震動等が激しいなど、受信機の機能に影響を与える恐れのある場所には設置できない
- ひとつの防火対象物には、原則として1台の受信機を設置し、監視するものであること。ただし、同一敷地内に2以上の建築物(管理権原が同一の場合に限る)で次のいずれかにより集中管理ができる場合にはこの限りでない
※建築物の業態や利用形態等を考慮して、以下のように1台の受信機でも他の防火対象物の監視ができると判断される場は、令第32条を適用して1台の受信機の監視も可能
- 防災センター等(常時人のいる場所)に設置してある受信機に、他の建築物に設置してある受信機からの火災信号等(移報)を受信し、監視できる場合
- 受信機設置場所を1箇所とし、各棟を監視する複数の受信機を集中させ監視させる場合
- 放送設備の設置を必要とする防火対象物にあっては、増幅器等(操作部を含む)と受信機を併設する。受信機設置場所が不明確な場合は、その出入口などに標識(火災受信所など)を設けること
- 一部の防火対象物では、地区音響再鳴動機能付きの受信機が必要(特定一階段防火対象物やカラオケボックス・ダンスホールなど)ただし最近の受信機は再鳴動機能が標準で搭載されていることが多い
感知器設置場所の要件
1.以下の要件を満たした、点検・操作に支障のない場所に設置する。
- 床面から受信機の音響停止スイッチ・地区音響停止スイッチまでの距離(高さ)(液晶パネルの場合はパネルの上端)が0.8~1.5m以内
- 離隔距離は、自立型は、背面0.6m以上(背面に扉がある場合、なければ壁に直でOK)、左右0.5m以上、前面2m以上
- 壁掛型は、左右0.3m以上、前面1m以上
2.直射日光、外光、照明などにより、火災灯、表示灯などの点灯が不鮮明とならない位置、かつ地震動などの震動による影響を受けない、堅牢かつ傾きのない位置に設置する
住宅用火災報知器の設置場所
住宅用火災報知器の設置場所の要件は以下の通りです。
- 就寝に使用する場所(寝室、子ども部屋、客間など)
- 就寝に使用する場所が2階以上にある場合は寝室のある階の階段の踊り場(天井または壁)
- 階段部分に警報器を設置しない階が2階以上連続する場合(3階建て以上)、警報器を設置した階から2階離れた居室のある階(避難階を含む)の階段
- 台所(各市町村の条例で設置が義務付けられている場合)
火災報知器は設置基準や場所を守って適切に設置しよう
火災報知器の種類や設置基準、設置場所について解説しました。火災報知器は設置が義務付けられており、万が一の火災発生時に命を守るために大切な役割を果たします。要件を確認し、適切な場所に設置を怠らないようにしましょう。
関連記事
ソフト防災・ハード防災とは?災害対策の具体例を解説
地震被害後本当に困ったことは「トイレ」!やっておきたい備えとおすすめ商品を解説