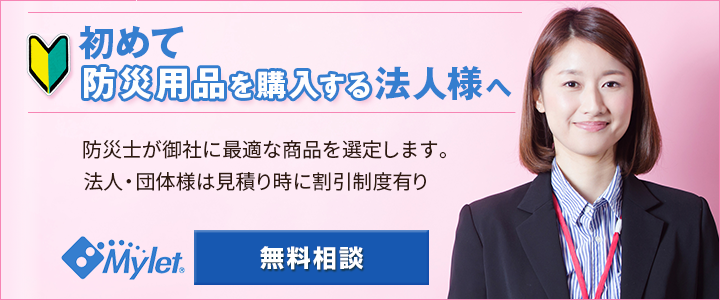災害発生後はライフラインや物流の停止による供給力低下により、生活に必要となる物資の慢性的な不足が発生することは珍しくありません。その際に国や自治体から避難者や被災者へ届けられるのが支援物資です。ただし支援物資はすぐに届くわけではないため、ある程度家庭で災害への備えを行っておく必要があります。本記事では、支援物資の内容や国や自治体の支援の仕組み、支援物資が届くまでの日数の目安、備蓄として必要なものについて解説します。
「水のいらない」災害用トイレはこちら
Contents
支援物資の内容や提供元
支援物資に関する基本情報をまずは押さえておきましょう。
支援物資とは
支援物資とは、災害発生などの緊急時に避難者や被災者に対して配られる生活必需品をはじめとした物資のことです。
支援物資の内容
支援物資は、被災者の命と生活環境に不可欠な物資として以下の「基本8品目」が提供されることが多いです。
- 食料(パン、米、肉、野菜、飲料水等)
- 大人用おむつ
- 毛布
- 携帯トイレ・簡易トイレ
- 乳児用粉ミルクまたは乳児用液体ミルク
- トイレットペーパー
- 乳児・小児用おむつ
- 生理用品
さらに状況に応じて、以下の物資も支援物資として集められ提供されます。
- 避難所環境の整備に必要な物資(プライベートスペース設置用のボードや段ボールなど)
- 冷暖房機器
- 感染症対策に必要なマスクや消毒液等
支援物資の提供元
支援物資は以下のように国や地方自治体といった公の組織のほか、私的な団体や個人からも提供されます。
- 被災地方公共団体
- 国
- 支援地方公共団体
- 企業・団体
- 個人、海外(外国政府、国際機関等)など
国や地方公共団体の場合、あらかじめ災害に備えた備蓄品を支援物資として提供します。また、企業や関連団体と連携し、企業の製品や商品を支援物資として提供することもあります。
個人が支援物資を被災地へ送付することも可能ですが、あくまで「現地で必要とされていて、なおかつ必要な時に、必要な場所まで届けられる場合」に限り送付することを全社協 全国ボランティア・市民活動振興センターでは推奨しています。被災地に個人から多くの支援物資が送付されてくると、内容確認や仕分け、分配などの負担や手間が逆にかかってしまうためです。
個人で支援物資の送付を検討しているときには、個人からの支援物資を受け付けている自治体や団体などの窓口を通じて必要なもののみ送る、支援物資ではなく義援金や寄付という形で支援する、といった方法を取りましょう。
支援物資が被災地や被災者のもとへ届けられる方法や仕組み
各所から集められた支援物資が被災地や被災者のもとへ届けられる方法や仕組みについて順に解説します。
プッシュ型支援
プッシュ型支援とは、被災地方団体から具体的な支援物資の要請が来る前に、国が被災地へ支援物資を緊急輸送する方法です。被災現地では混乱状態にあり、災害規模や被災者数などの正確な情報の把握や、物資の供給能力が平時より著しく低下します。そのため、国では要請を待たずスピーディな支援を提供する目的で、プッシュ型支援による支援物資輸送を行っています。
平成23年3月の東日本大震災の教訓を経て、平成28年に発生した熊本地震の際からプッシュ型支援による支援物資の輸送が開始されました。平成30年7月豪雨発生時には、国と関連団体、企業が連携した民間によるプッシュ型支援が行われた事例があります。(一社)日本即席食品工業協会を通じて食品メーカーである日清食品は農林水産省からの支援依頼を受け、最終納品指示から約22時間後に、岡山・愛媛の両県に合わせて約2万1,000食の即席麺と割り箸を供給しました。
参考:農林水産省_避難所と支援物資
迅速かつ効率的な支援物資の提供を実現するために、国では令和2年度より「物資調達・輸送調達等支援システム」、さらに令和7年4月からは機能追加などの改善が行われた「新物資システム(呼称B-PLo(Busshi Procurement and Logistics support system))」の運用を開始しています。物資システムは平時に地方公共団体の物資の備蓄状況を容易かつ迅速に把握する役割も担っています。
プル型支援
プル型支援とは、被災地方団体からのヒアリングを通じ、要請があった支援物資を提供する方法です。プッシュ型支援が行われる前から採用されている支援物資の提供方法で、現在もプッシュ型支援と併用されています。
プル型支援には、大規模自然災害発生時に物資やサービスなどの支援をワンストップで提供する、日本発の民間主導による緊急災害対応アライアンス「SEMA(シーマ)」が稼働しています。国内の民間企業45社とNPO6団体が連携し、平時から加盟企業や団体が持つ物資・サービスなどをリストとして集約することで、災害発生時には各社が提供できる物資を迅速に被災地へ提供できる体制を整えています。
支援物資が届くまでの日数の目安と日頃の備蓄の重要性
支援物資は必要なものがすぐに手元に届く、というわけではありません。支援物資が届くまでの日数の目安と、日頃の備蓄の重要性について解説します。
支援物資が届くまでの日数の目安

災害によって自宅では命の危険がある、または自宅の損壊・倒壊により住めなくなってしまった場合、避難所へ一時的に身を寄せることになります。避難所には一部備蓄されている支援物資もあるケースもありますが、すぐに提供されるのはほんのわずかです。国や自治体、関連団体や企業などから集められた支援物資が被災者のもとへ届くには、食料などの緊急性の高いもので約3〜7日後と言われています。
さらに、災害発生後から時間が経過するにつれて、支援物資のニーズも変化していきます。たとえば食料や水などの生きるために必要最低限以外の物資も求められるようになるでしょう。国土交通省では、被災地外から支援物資が届くようになるのは最速でもインフラ復旧が完了した3日後、支援物資物流が本格化し、支援物資が物資集積拠点に到着するようになるまでに1ヶ月かかるとしています。さらに災害発生から1ヶ月以降は生活必需品の支援物資の安定供給できる体制はできているものの、支援物資へのニーズの多様化への対応が求められます。
参考:国土交通省_首都直下地震等に対応した支援物資物流システム
支援物資が届くまでは家庭の備蓄が重要
支援物資が集められ、被災者のもとへ届くのには時間がかかります。さらに自治体によっては観光客など備えのない被災者への支援を優先する場合もあり、必要な支援物資が届くまでに家庭での備蓄を強く推奨しています。
家庭での備蓄は最低3日、できれば1週間分がおすすめです。食料はもちろん、水道が止まってしまえばトイレも使用できません。家族分の食料や非常用トイレなど、必要な備蓄を日頃から行うようにしましょう。
持ち出し避難、在宅避難用の防災グッズと量については以下の記事でくわしく解説しています。
防災グッズに絶対必要なものを自宅避難・持ち出し避難に分けて解説
まとめ
支援物資の概要や内訳、届くまでの日数や提供方法について解説しました。国や自治体はもちろん、企業や個人などの善意によって被災者まで届けられる支援物資は災害発生後心強いものとなりますが、実際に手元に行き渡るまでには時間がかかります。支援が届くまでの間を踏まえて、常日頃から家庭で災害への備えを行っておくことが重要です。