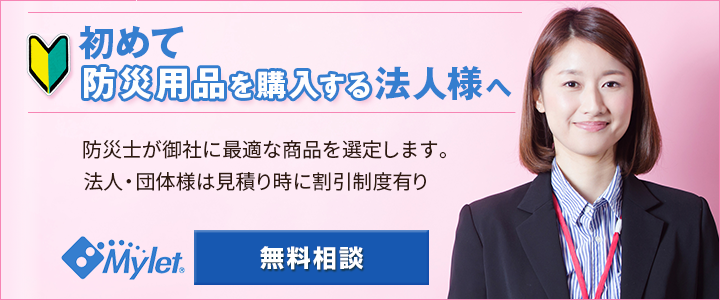Contents
法人企業に防災用品の備蓄が求められる理由
災害大国と呼ばれる日本では、地震や台風、豪雨などの災害がいつ発生してもおかしくありません。災害は自宅にいるときだけでなく、事業所やオフィスで働いているときにも発生します。防災用品の備蓄をはじめる一般家庭は増加傾向にありますが、防災用品の備蓄が進まない、まったく準備をしていないといった企業や法人も存在します。
企業や法人が防災用品を備蓄する理由や重要性をまず解説します。
従業員や顧客の命と安全確保
災害発生時、もっとも優先される事項が「人命救助」です。災害が起きたら、企業・法人としてまずは従業員や顧客などの利害関係者の命と安全を確保する必要があります。災害発生直後や二次災害から人命を守るため、さらに災害発生後からライフラインや救援物資が届くまでの間生き延びるために必要となるのが防災用品です。一人でも多くの命を助けるためにも、企業・法人として必要な防災用品を備蓄しておく必要があります。
事業継続計画(BCP)体制の構築
大規模災害発生時、従業員や利害関係者の人命と安全を確保した後次にやるのが事業継続への取り組みです。知的財産やデータなどの経営資源の状況を確認し、必要に応じて復旧作業を行います。地震や津波、台風などの大規模災害発生時をはじめ、非常時でも事業を継続するための計画や仕組みを構築しておくのが「事業継続計画(BCP)」です。
法人や企業が準備する防災用品には、事業をできるだけ早く再開し、継続するためのものも含まれます。たとえば停電時でも事業を継続できるように非常用発電機を確保しておく、従業員が出社できなくても自宅から業務ができるようにリモートワークの仕組みを構築しておく、データのやり取りや連絡をスムーズに行えるようにクラウドを導入しておくなどです。
事業継続を目的とした防災用品は発電機や非常用サーバなどの機器類が多いため、災害発生時にスムーズに運用できるように、日頃から点検やメンテナンスを行っておくことが重要です。
地域への貢献
内閣府発表の企業防災ページでは、「企業は地域の一員として、被害の軽減及び災害復旧・復興に貢献すること」と記載されています。災害発生時には自分で自分の身を守る「自助」、周りの人と協力する「共助」、国や自治体などからの支援を受ける「公助」の3つの取り組みを組み合わせて災害の被害軽減につとめます。企業は「共助」の面で地域の一員として、地域住民へ災害物資や避難所を提供したり、災害復旧や復興の助力となったりすることが求められています。防災用品を備蓄しておくことは、災害を通じた地域への貢献にもつながります。
企業・法人が備蓄すべき防災用品と目安の量
企業・法人として防災用品の備蓄を勧めようと思っていても「何をどの程度準備すればよいか分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。企業・法人が備蓄すべき基本的な防災用品と目安の量を以下にまとめました。
|
用途 |
防災用品 |
|
身を守るためのもの |
・ヘルメット ・軍手 など |
|
救助や救命に必要なもの |
・救急医療薬品類 ・衛生用品 ・工具セット など |
|
災害対策本部の設営に必要なもの |
・乾電池・非常用電源 ・懐中電灯 ・携帯ラジオ ・メガホンまたは拡声器 など |
|
避難生活に必要なもの |
・保存水 ・主食(アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺など) ・毛布 ・防災用トイレ など |
|
帰宅支援の道具 |
・携帯食料 ・携帯用保存水 ・ホイッスル ・ポリ袋 ・運動靴 ・周辺の地図 など |
|
事業継続に必要なもの |
・モバイルバッテリー ・発電機 ・電源タップ ・延長ケーブル など |
「東京都防災ホームページ」によると、備蓄する量は災害発生からライフラインが復旧するまでの「3日分(72時間)」です。保存水なら3L×3日分、主食は3食×3日分で9食分用意しましょう。備蓄が必要となる目安の人数(従業員数、避難受入数)×3日分の防災用品を備蓄します。
参照:東京都防災ホームページ
マイレットの防災用商品一覧
防災用品を準備する前に確認しておきたいこと
防災用品をそろえる際には、事前に確認し準備をしっかり行うことが重要です。以下では、確認すべき項目を解説していきます。
防災用品を準備する目的を確認
自然災害は地震、洪水、台風、火災などが考えられます。これらの災害について、さまざまな問題(公共交通機関の運行停止、電気・ガス・水道が使えない、主要幹線道路の通行止めなど)が発生する可能性があります。
このような場合に備えて、防災対策を行う目的として「生存に必要な防災用品の確保」が重要であるといえます。このようにして、災害用の備蓄品を準備する目的を明確にすることで企業全体で災害対策に取り組むことができます。
必要な防災用品を計算
まずは従業員数を正確に把握し、必要な防災用品の数を計算しておきましょう。
防災用品の必要量については、在籍人数に来訪者(お客様)を想定した数を用意することが一般的です。在籍人数には正規社員だけでなく、非正規社員や派遣社員も含めることも重要です。従業員数は変更になることが多いので定期的に更新しておくとよいでしょう。
自社にとって必要な防災用品がどれくらいなのかを、根拠に基づき計算し適切な防災備蓄品を準備することが大切です。
災害時や防災用品を使用する場面を想定
防災用品は各アイテムによって適切な場所に保管しておく必要があります。例えば、ヘルメットであれば災害が発生したらすぐに着用できるよう、従業員のデスクに収納するとよいです。会議室など比較的大きな部屋は、救護室や休憩所として活用できるので、救急箱や毛布などは会議室内や周辺に収納しゅうのうしておくなど実際に使用する場面を想定して保管場所を検討しておきましょう。
法人・企業の防災用品の選び方

法人・企業が備蓄する防災用品は業種や季節、地域の特徴などによって異なります。前述の防災用品はあくまで基本的なものです。自社で必要な防災用品を選ぶときのポイントを順に解説します。
地域の特性や季節を考慮する
地域の特製や季節によって、必要となる防災用品の種類や備蓄量は異なります。たとえば事業所があるのが寒冷地、または冬の場合備蓄の毛布1枚のみでは寒さがしのげない可能性が高いです。寒冷地や寒い季節では備蓄する毛布の量を増やしたり、断熱シートやマットレスなどを追加したりといった工夫をしましょう。感染症の流行期には、避難生活での感染を防ぐために備蓄品の中にマスクを準備するのも必要です。
気温の上がりやすい地域や季節は、熱中症にかかるリスクが高くなります。1日3Lの飲料水では不足する可能性が高いため飲料水の量を増やすようにしましょう。
全従業員分+余裕のある分を確保する
企業・法人が備蓄する防災用品は、雇用形態に関わらずオフィスで働くすべての従業員分が必要です。正社員の分だけでなく、パートやアルバイト社員、派遣社員の人数も確認し、必要な分を用意しましょう。特に規模の大きな組織や事業所の場合、従業員の入れ替わりや異動が頻繁にあるため、人数が変動する機会が多いことがあります。毎月の正確な全従業員の人数を把握し、防災用品の備蓄に過不足がないかを定期的にチェックしておきましょう。
全従業員分に加えて、取引先などの来客分や避難してきた近隣住民の分も踏まえて余裕を持った量を備蓄するのがおすすめです。
保存水や食料は長期保存できるものを選ぶ
企業・法人向けの防災用品として備蓄する保存水や食料は、長期保存できる「防災用」のものを選びましょう。一般的なレトルト食品やインスタント食品などは、年単位の長期保存を前提としていません。「災害時に使おうとしたら保存水や食料の期限が切れていた」ということがないように、企業や法人向けの防災用品には5年間など長期保存ができる防災用の保存水や食料を選ぶと安心です。
備蓄している保存水や食料は、定期的に消費期限のチェックを行いましょう。使った分だけ補充しながら備蓄する「ローリングストック」を活用するのも有効です。
事業所やオフィスの特徴を考えたものを用意する
基本的な防災用品のほか、事業所やオフィスの特徴をふまえて必要なものを合わせて用意しておきましょう。たとえば社用車が多いなら車載用の防災用品も合わせて用意しておく、ジャッキや予備のバッテリーなど車を動かすための機器も用意しておくなどです。工場や大きな事業所など敷地の面積が大きい場合は、自転車があれば災害時に周囲の安全や避難経路の確認がスピーディにできます。
保管スペースとの兼ね合いを考える
従業員に近隣住民の分を考えると、大量の防災用品の備蓄が必要です。防災用品を備蓄するスペースとの兼ね合いを考えましょう。たとえば使わないときにはコンパクトなサイズにまとめられるなど、省スペースのものを選ぶのもおすすめです。
備蓄品の保存場所にも気を付けましょう。災害発生時にすぐに利用できるようにと防災用品の備蓄スペースを通路に設けるのは厳禁です。災害時の避難や誘導の邪魔になるだけでなく、消防法違反となる場合もあります。専用の保管庫を用意し、社員へ保管庫の場所や管理方法、災害時の利用方法などを社内に周知しておくことで、災害時の混乱を防いで防災用品を運用できます。
防災用品の準備ができたら保管場所を社内周知
従業員の人数によっては、大量の防災用品が必要となります。災害時にすぐに利用できるように、通路などに保管しているケースもありますが、災害発生時の避難通路の確保が困難になりますので専用の保管庫を用意しましょう。
防災用品を収納したら、防災用品・備蓄品リスト、保管庫の場所、災害時の利用方法などを社内に周知させることで、災害発生時の混乱を防止することができます。
企業・法人として防災用品の備蓄を進めておこう
企業・法人が防災用品を備蓄する重要性と、防災用品の目安量や選び方を解説しました。防災用品を備蓄しておくことで、従業員の命を守るだけでなく、事業の継続や地域への貢献にもつながります。企業や法人としての社会的責任を果たすためにも、防災用品の備蓄をはじめましょう。