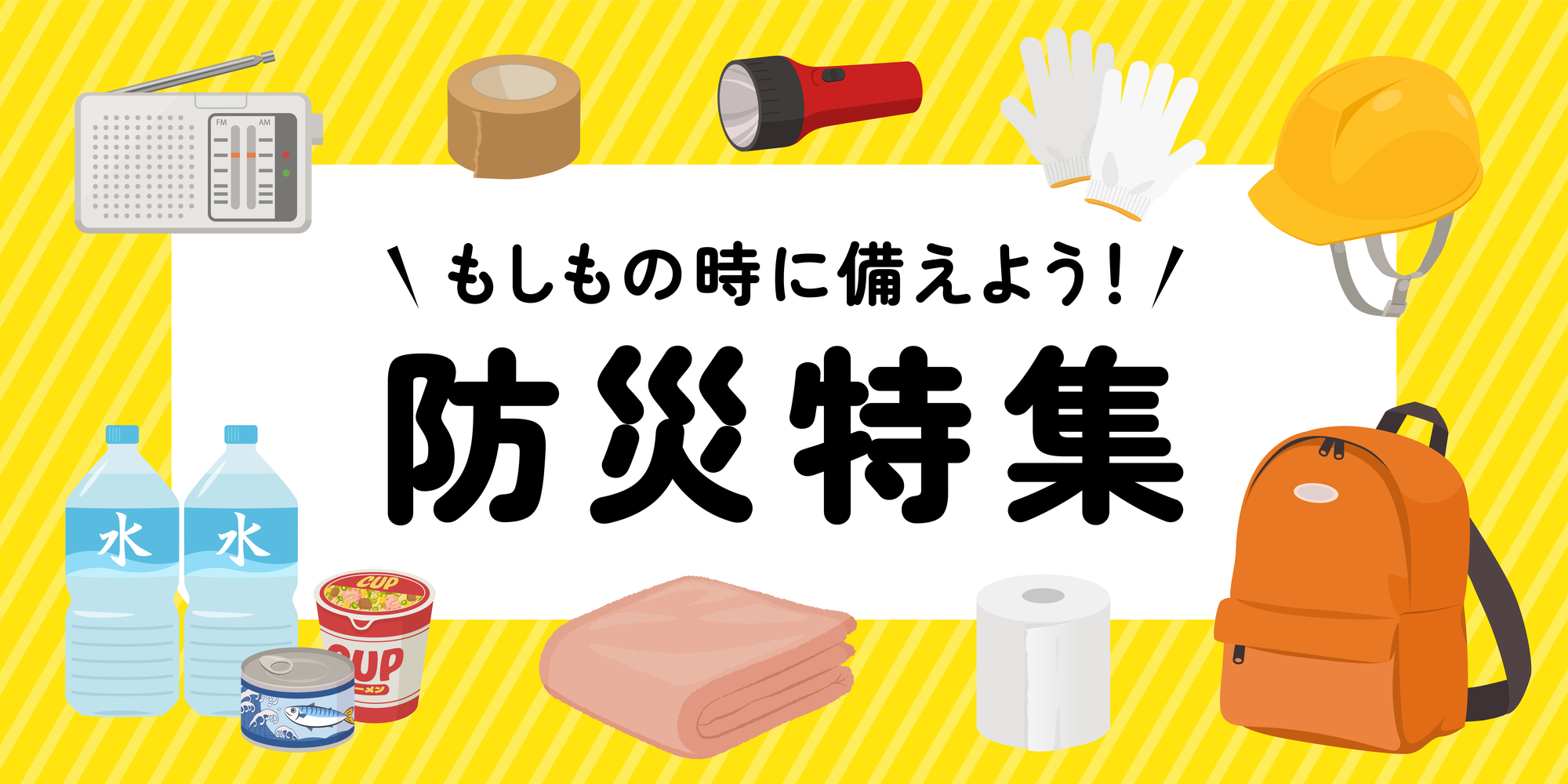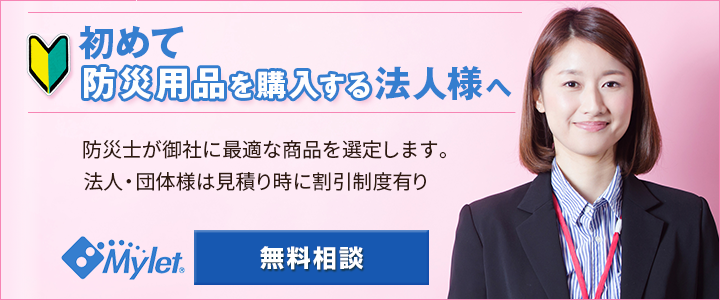企業の災害時や非常時、事業を継続させるための取り組みとして「BCP」の立案や推進を検討している企業も増加しています。一方で、「BCPをはじめようと思っていても何をすべきか分からない」「BCPに取り組もうと思っていても、防災対策や備蓄と何が違うかわからない」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。今回の記事では、企業のBCPに関するアンケート調査を踏まえて、企業のBCPにおいて今後優先して取り組む強化策や、防災備蓄品整備について解説します。
Contents
BCPとは企業が事業を継続するための計画
BCP(Business Continuity Plan)とは日本語で「事業継続計画」を指し、企業が以下のような危機的状況下や非常時においても事業を継続するための方法、手段などをあらかじめ取り決めておく計画のことです。
- 大規模災害
- テロ攻撃
- ウイルスパンデミック
- システム障害
- 企業の不祥事など
近年災害の甚大化やサプライチェーンの多様化などを背景に、日本国内では内閣府の「事業継続ガイドライン」や中小企業庁での「中小企業BCP策定指針」の公表をはじめ、国を挙げてBCPの策定を推進しています。
BCPの概要や策定の手順については、以下の記事で詳しく解説しています。
BCP(事業継続計画)とは?企業としてやるべき準備や注意点を解説
アンケート結果から見る企業がBCPで優先して取り組む強化策とは
企業で優先して取り組むべきBCP対策の参考になる、アンケート結果から見た傾向や対策方法を順に解説します。
防災備蓄をすでに実施している企業が多数
備蓄サービスの専門会社Laspyが全国の企業の総務担当者を対象に行った「2024年度 最新版 企業の総務担当者を対象とした防災対策状況調査」では、「企業が今年に入ってから具体的に実施した防災対策や災害対策」として、以下が挙げられました。
- 「防災備蓄品(食料、水、医薬品、生活必需品など)の整備」43.2%
- 「社内での避難訓練や防災マニュアルの策定・整備」33.8%
- 「緊急連絡網や安否確認システムの導入」26.3%
- 「従業員向けの防災教育や研修の実施」20.7%
- 「事業継続計画(BCP)の策定・見直し」16.4%
- 「防災関連機器や設備の導入・強化」16.9%
多くの企業の防災対策として、防災備蓄品の整備がもっとも行われている事項であることが分かりました。防災備蓄は企業の防災対策としてすでに行っているところが多いことに加えて、BCPと防災対策を兼ねた施策をはじめたいときにも、取り組みやすく選択されやすいことが背景にあります。
ほかにも、防災マニュアルや緊急連絡網などの整備といった、円滑な避難行動や情報伝達を通じて従業員の安全を確保する取り組みを優先的に行っている企業が多いことも分かりました。
一方で、BCPの策定や見直し、防災関連機器や設備の導入に関しては取り組んでいない企業も多く、長期的かつ総合的なBCPや防災対策までまだ手が回っていない企業が多いとも言えるでしょう。
優先すべき強化策も、防災備蓄が1位に
「企業の事業継続計画(BCP)において今後優先して取り組みたい強化策」については、以下の事項が挙げられました。
- 「防災備蓄品の整備」57.3%
- 「緊急連絡網・安否確認システムの導入」33.3%
- 「従業員の避難訓練の実施」30.5%
- 「重要データのバックアップ・クラウド保存の整備」26.3%
- 「社内防災マニュアルの策定・更新」23.9%
- 「従業員向けの防災教育・研修プログラムの実施」21.6%
防災対策と同様、BCPでも防災備蓄品の整備を優先すべき強化策として挙げる企業が多くありました。また、従業員の安全を確保するための事項に加えて、BCPでは企業の財産と成る情報管理や、従業員の防災意識を高めるための取り組みを強化したいと考えている企業も多くあることが分かります。
防災備蓄で発生するさまざまな課題
「防災備蓄品(食料、水、医薬品、生活必需品など)の整備」を具体的に実施した防災・災害対策と回答した企業を対象に、防災備蓄品に関して直面している具体的な課題について質問したところ、以下の回答が集まりました。
- 「備蓄品の保管スペースの確保が難しい」50%
- 「備蓄品の管理や定期的な更新が行き届いていない」38%
- 「コストの問題で十分な備蓄ができていない」35.9%
- 「備蓄品の選定に関して適切な判断ができていない」28.3%
- 「備蓄品の使用期限切れや劣化」21.7%
- 「特に課題は感じていない」13%
防災備蓄を行っている企業の半数が、備蓄品の保管スペース確保を課題としていることが分かりました。また、備蓄品の管理や更新、選定なども課題として挙げられています。企業の防災備蓄は規模や従業員数が多いほど備蓄の量も多くなります。中には、避難所や帰宅困難者向けの援助用の備蓄をしている企業もあるでしょう。
防災対策やBCPの取り組みとして防災備蓄をはじめるには、保管に関する課題を踏まえつつ効率的に備蓄を進めることが重要です。
参考:PR TIMES_調査レポート
企業がBCPとして防災備蓄を行うポイント

防災備蓄の重要性や必要性は踏まえつつも、スペースや備蓄品管理、コストなどの点で課題がありなかなか防災備蓄が進まない、うまくいかないという企業も多いことが分かりました。今後防災対策やBCPのために企業が防災備蓄を行う際に、覚えておきたいポイントを解説します。
自社の備蓄に必要な量を把握しておく
防災備蓄は最低3日間、できれば1週間分用意しましょう。実際に必要となる防災備蓄の量は、従業員数や企業の地域性などによっても左右されます。自社の備蓄に必要な量や用意すべきものを把握し、まずは無理のない範囲から備蓄をはじめることをおすすめします。
企業が用意する防災備蓄の量や種類については、以下の記事で詳しく解説しています。
企業・法人向け防災用品・防災グッズを災害別に防災士が解説します
特に企業の防災備蓄では、「非常用トイレ(災害用トイレ)」がもっとも不足しているという調査結果もあります。断水時、飲料水だけでなくトイレも使用できなくなります。非常用トイレ(災害用トイレ)の備蓄もしっかりと行いましょう。
「水のいらない」災害用トイレ一覧はこちら
ローリングストックを活用する
ローリングストックとは、備蓄する食料品や水を多めに購入しておき、賞味期限が近くなったものから消費し、新しいものを順次ストックしていく方法です。おもに個人や家庭での備蓄に利用されていますが、企業の防災備蓄にも応用できます。
ローリングストックを活用することで、賞味期限や消費期限切れを防いで備蓄が可能です。ローリングストックの方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
ローリングストックとは?日常備蓄での方法やメリット、上手な備蓄のポイントを解説
フェーズフリーを活用する
フェーズフリー(Phase Free)とは、日常でも非常時でも役立つようにデザインされたモノやサービス、または考え方のことです。フェーズフリーを活用することで、企業で日常業務などで使用しているものを災害時にも活用できるようになり、備蓄や管理の負担を軽減できる可能性があります。
フェーズフリーの概要や事例については、以下の記事で詳しく解説しています。
フェーズフリーとは?メリットやおすすめ商品を防災士が解説
まとめ
企業の防災対策やBCPで優先すべきと考えられている防災備蓄と課題、上手に行うポイントを解説しました。防災備蓄をはじめれば、企業の防災対策とBCPの両面で有効です。成功するポイントなどを踏まえて、上手に備蓄をはじめましょう。