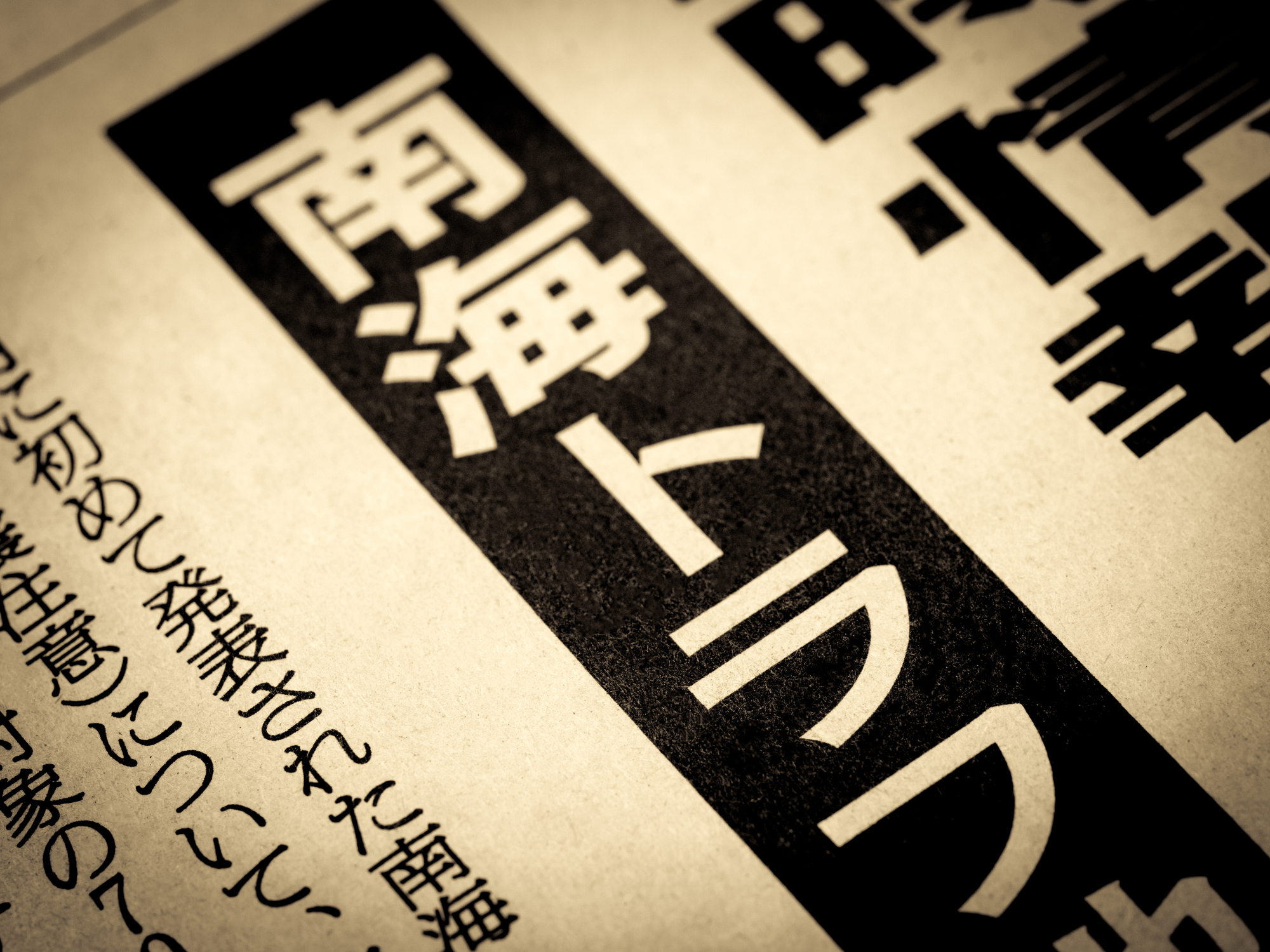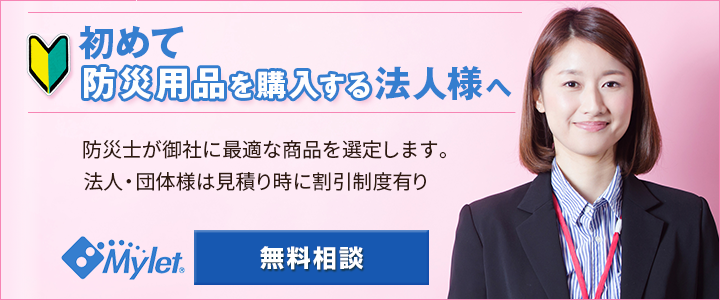近い将来の発生が予測・懸念されている災害に南海トラフ巨大地震があります。発生に備えるために、国では定期的に南海トラフ巨大地震の被害想定を発表しています。令和7年3月に新被害想定が発表され、前回の発表からの内容の更新、見直しが行われました。
今回の記事では、発表された南海トラフ巨大地震の新被害想定の内容を踏まえて、避難が必要となる範囲や備えておくべき備えや備蓄について解説します。
Contents
南海トラフ巨大地震の新被害想定
令和7年3月に政府の中央防災会議で発表された南海トラフ巨大地震の新被害想定の内容を、各項目ごとに解説します。
地域ごとの被害想定
南海トラフ巨大地震によって大きく被災する地域が異なるケースごとに、以下の新被害想定が出されています。
| 大きく被災する地域 | 全壊および消失棟数 | 死者 |
|---|---|---|
| 東海地方 | 約96万6000棟〜234万棟 | 約6万5000人〜29万8000人 |
| 近畿地方 | 約96万6000棟〜233万棟 | 約4万1000人〜28万2000人 |
| 四国地方 | 約95万2000棟〜232万4000棟 | 約3万人〜23万8000人 |
| 九州地方 | 約98万1000棟〜234万棟 | 約2万9000人〜24万人 |
地震の揺れの想定
南海トラフ巨大地震は最大マグニチュード9クラスの激しい揺れが広範囲に及ぶとされています。地震の揺れは震度6弱以上が神奈川県から鹿児島県にかけての24府県600市町村、震度7が静岡県から宮崎県にかけての10県149市町村に及ぶと想定されています。
津波の想定
南海トラフ巨大地震は、大きな地震とともに大津波も広範囲に及ぶとされています。津波は3メートル以上が福島県~沖縄県にかけての25都府県、10メートル以上が関東~九州にかけての13都県、さらに高知県と静岡県では局地的に30メートルを超える可能性があると想定されています。
液状化の想定
一般的に震度5以上の地震が発生すると、地盤が液状になる「液状化現象」が発生する恐れがあります。液状化現象は臨海部や沿岸地、埋立地などで発生しやすい傾向にあります。
南海トラフ巨大地震では、震度5以上の揺れが想定されているエリアで液状化が発生すると想定されています。特に東海・近畿・四国・九州の各都市の中でも、大阪府や愛知県の都市部エリアは液状化による被害想定が高めとなっています。
上下水道の被害
南海トラフ巨大地震は地震の揺れや津波による死者や建物への被害だけでなく、電気やガス、上下水道といったライフラインへの大きな被害も想定されています。
上下水道への被害は、地震発生直後、首都圏、東海地方、近畿地方、四国地方、九州地方の幅広い範囲で断水の発生が予想されています。特に以下のエリアでは、高い断水率が予想されています。
- 断水率90%以上:静岡県、三重県、高知県、大分県
- 断水率80〜89%:山梨県、奈良県、徳島県、宮崎県
- 断水率50〜79%:岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、和歌山県、岡山県、愛媛県
ほかにも断水率は低いものの、首都圏を含む幅広いエリアで断水が予想されています。
発生後1日、1週間と時間が経つごとに断水は少しずつ解消されていきますが、被災1ヶ月後でも断水が解消されていないエリアも多く、特に静岡県では24%、徳島県では19%、高知県では30%と被災1ヶ月後でも高い断水率が想定されています。
停電の被害
南海トラフ巨大地震発生後、東海地方や近畿地方、四国地方、九州地方の幅広いエリアや首都圏での停電が想定されています。特に大きな揺れが想定されるエリアでは、地震発生直後90%以上の高い停電率が予測される都道府県がほとんどです。
被災4日後には停電が解消されているエリアが多くなるものの、静岡県や三重県、和歌山県、徳島県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県、さらに神奈川県と東京都の一部エリアは被災1週間後も停電が続くと予測されています。
ガスの被害
南海トラフ巨大地震発生後、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県でガスの供給停止が予想されています。特に徳島県と高知県は100%、宮崎県は62%と高い供給停止率が想定されています。
供給停止率の高い地域は、発生1週間後でもガスが復旧していない恐れがあります。
電話・インターネットの被害
南海トラフ巨大地震では、発生後1140万件(全体の不通回線率31%)の電話・インターネットの不通回線が発生すると予測されています。発生1日後には全体の不通回線率は21%、1週間後には徐々に電話やインターネットの不通は解消されるものの、約1ヶ月後でも数%の不通回線が発生している地域もあります。
携帯電話については、発生直後の不通率は少ないものの、地震発生1日後は安否確認や家族連絡などで通話が集中し、特に東海地方と近畿地方でつながりにくくなることが予想されています。
防災対策による南海トラフ巨大地震の被害軽減想定
南海トラフ巨大地震では、以下のような防災対策を行うことで被害軽減も想定されています。
- 建物の耐震化により死者数約73,000人→約77%減の約 17,000 人
- 家具等の転倒・落下防止対策により死者数約5,300人→約66%減約1,800人
- 全員が発災後すぐに避難を開始した場合、津波による死者数に約2.9 倍~約14.1 倍の差が想定される
- 地震時の電気火災の発生を抑制する感震ブレーカーの設置を促進することで、火災による死者数約21,000人→約52%減の約10,000人
南海トラフ巨大地震発生時の避難や対策が求められる地域

内閣府では、南海トラフ巨大地震発生に特に警戒・かつ避難が求められる地域として「南海トラフ地震防災対策推進地域」および「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」を指定しています。
南海トラフ地震防災対策推進地域に該当するのは以下の条件を満たす地域です。
- 震度6弱以上の地域
- 津波高3m以上で海岸堤防が低い地域
- 防災体制の確保、過去の被災履歴への配慮が求められる地域
南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に該当するのは以下の条件を満たす地域です。
- 津波により30cm以上の浸水が地震発生から30分以内に生じる地域
- 特別強化地域の候補市町村に挟まれた沿岸市町村
- 同一府県内の津波避難対策の一体性の確保
※ 浸水深、浸水面積等の地域の実情を踏まえ、津波避難の困難性を考慮
具体的な地域については、内閣府の資料にて公開されています。
参考:内閣府_南海トラフ地震防災対策推進地域の指定
南海トラフ巨大地震でやっておくべき備蓄
南海トラフ巨大地震に備えて、ほかの災害発生への備えと同じく避難用の「非常用持ち出し袋」と在宅避難用の「自宅の備蓄」を準備しておきましょう。
備蓄の内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
防災グッズに絶対必要なものを自宅避難・持ち出し避難に分けて解説
特に南海トラフ巨大地震は被害想定地域が広範囲に及び、直接的な被害だけでなくライフラインの寸断による停電や断水、インターネットや電話の不通などが発生する可能性が高いです。また、地震の規模が大きいほどライフラインの復旧には時間がかかってしまいます。
食料や水といった基本的な備蓄のほか、非常用トイレ(災害用トイレ)やガスコンロなどの備蓄も忘れずに準備しておきましょう。
「水のいらない」災害用トイレ一覧はこちら
まとめ
南海トラフ巨大地震の新被害想定の内容や備蓄について解説しました。被害想定は定期的に更新されるため、常に最新の情報をチェックし必要な備蓄を進めておきましょう。